『首都圏自治体の攻防』(ぎょうせい、2001年)より抜粋
現在までに形成されてきた東京都市圏の構造的特徴をいうならば、その構造が、諸機能の集中・集積によって作り上げられ、そして、今度はその都市構造がさらなる集中・集積を生み出してきたという相乗効果にあるという点に集約される。そもそも大都市圏域が、その活力を生みだし、しかもダイナミックな活動を継続するためには、それに見合うだけの潜在力(ポテンシャル)と、それを十分に現実化するだけの誘引圧力(マグニチュード)がなければならない。その法則に従えば、東京都市圏は戦後50年以上の時間的経過の中で、その組み合わせを存分に生かして世界にも例を見ない効率的な巨大都市圏を実現してきたといえよう。
では、この巨大都市圏の今後、すなわち将来を考えるときに、果たしていかなる手だてが有効なのであろうか。通常、地域の将来を考えるにあたってとるべき手法は、シナリオライティングである。社会経済状況等の与条件の変化を前提として、中期ないしは長期といった時間のスパンを設定して将来像を描きだすことになる。描くにあたっては、いくつかの主要な指標ごとの将来推計値を算出し、それに基づいてストーリーを作っていくのであるが、仮に将来推計によって社会指標、経済指標がインプットのデータとして導き出されたとしても、それを使って描き出される地域の将来像は、考え方の視点によって、プラス(楽観)側にもマイナス(悲観)側にもふれることになる。
その手法を東京都市圏の将来にあてはめるのであれば、シナリオは3通り考えられる。1つは、過去の集中、集積傾向が依然として進行するという見方で、もちろんこれからの時間の経過の中では急速なことも、また緩やかなことも起きようが、結果において、過去と似たような傾向になるというストーリーである。
2つ目は、英語の表現でいうところのスティタス・クオー、現状維持、すなわち横ばいのシナリオである。遠からずして現実となる成熟社会への転換にあって、過去に幾たびか経験した急激な伸びは、もはやこれからは起きえないことが予想される。こうした中での現状維持、あるいはゆるやかな漸増傾向という考え方である。
3つ目は、東京都市圏における集中・集積が一応の飽和に至ったと考え、これからは域内における分散が始まるというシナリオである。そもそも、いくつかの社会・経済指標についての現状分析と将来予測によれば、2010年を境にして人口は減少傾向に向かい、また、郊外から区部への通勤状況のバロメーターである鉄道の平均混雑率は1995年の187%が2010年には158%、2025年には122%(もう混雑していない)という状態となる。業務・商業機能の動向としての従業指数の増加率については、既に90年代後半には鈍化傾向となっており、小売吸引人口も、2015年頃をピークに都市圏全域で減少に向かう。こうした数値は、都市圏全体としての域内での分散傾向が現れていくというシナリオの後押しをしていることを意味している。
(1)東京都市圏内拡散の未来図-集中の終結
なんらかのきっかけで東京都市圏への集中メカニズムが変わった時、その次に来るステージは集中から分散での新しいメカニズムでの発生であるとの仮定を置くとするならば、これは明らかに、集中・集積が一応の飽和に至ったという第3番目のシナリオとなる。ではそのシナリオを採ったとすると、具体的に何がおきるのか、その判断を下すにあたっての視点は、2つである。1つは分散が東京都市圏の将来にうまく関与する場合、そして、もう1つは、分散傾向が、実は地域の将来にとってはプラス局面を生み出さない事態、例えば、都市圏の中での衰退現象が発生する場合である。
1)分散がうまくいく場合
1987年の閣議決定で具体化が現実のものとなった政府のブロック機関の移転が当初計画通りになされ、しかも、民間による業務集積が一定規模の人口のレベルにまで達し、業務核都市が順調に育成されるケースである。さらに、その拠点としての業務核都市間のアクセスが従来の放射方向に加えて、環状方向への整備が充分になされ、拠点とネットワークの相互作用が地域の将来を決定づけていくという見方が可能にならなければならない。これは、過去に蓄積されたストックをうまく生かしながら、今後は機能と資源の分散という形で新たな活力ある局面を生みだすという状況を想定することになる。
では、機能と資源の分散とは、具体的に何を指すのか。大都市の圏域構造からみれば、域内に自立する拠点が適正に配置されることが先ず必要となる。そして、国レベルでの大枠の概念設定、具体的な施策があるにしても、その責を現実に担う役割は、各自治体にまかされることになる。業務核都市を持つ10の自治体はもとより、それ以外の自治体も各々が存在意義をもった自立圏域を確立しなければならない。自立のための原動力としていかにして業務機能を集積させるのか。業務遂行のための財政力をいかに高めるのか。それぞれが現実的な知恵を絞り出さなければならない必要に迫られる。例えば、スケールメリット確保のための自治体同士の合併による機能の向上も、最近の傾向として、そのための一つの手段として捉えることができる。そして、これを相互にネットワークするために、既存の放射線状の交通網に環状方向の交通網を整備することが大前提になる。
2) 分散がうまくいかない場合
地域圏内での分散化傾向が進展するにしても、それが地域の発展につながらない場合もまた可能性としては、確かにありえるのである。社会の成熟化傾向の下で、社会指標、経済指標は、安定的な方向に向かうことの確率が高いことが予想されている。これは分け合うパイが増えないことを意味しており、十分なポテンシャル(滞在力)がないなかでの分配という形となってしまう。すなわち、集中から分散へのステップの中で資源(可能性)がうまくネットワークされずに、結果的に地域が衰退していくという状況の発生も考えられるのである。
単純化した構図でいえば、業務機能の多くを依然として東京の都心区に依存し、都市圏の多くの自治体がそこへの従業員の供給先としての地位から脱却できずに、基盤整備水準が低く固定化されたままのベットタウン的状況に甘んじることである。しかも、今後、増大する地域のニーズに十分対応できるだけの力を持たずに個々の自治体が張り合う状態もそれに拍車をかけることが考えられる。さらに、アクセスの整備をとってみると、過去の強固なまでの放射方向の基盤整備のレベルに対して、環状方向の整備が十分なレベルにまで達成されずに置かれてしまう状態がこの場合には想定される。
(2)自治体間の攻防の発生の可能性
分散がうまくいくのか、否か。ポテンシャルとマグニチュードの組み合わせが、現在までの東京都市圏を形成してきた原動力であるとするならば、これからの地域の将来を考えるにあたっても、この組み合わせがどうなるかを前提として論を進めればよいことになる。
一つ確かなことは、集中傾向から分散傾向へのシフトは、ポテンシャルの側に変化が表れることを意味している。すなわち社会の成熟化は人口が減少に向かうという点に典型的に表れているように、量としての供給力の衰退であり、同時に、都市における各種需要の発生も下降することになる。これは過去の日本社会が置かれてきた量的不足に対して、量的供給で対応してきたスタンスに変化が生じることを意味する。すなわち、人や企業や公的セクターにあっても、量的不足であるから決定を急がねばならない、多様な選択の余地はないといった事態は、もはや前提とはならないのである。
今までのような、需要を生み出す側が供給されるものを受動的に受け入れざるを得なかったという立場が、ここで初めて、主体的に取捨選択できるという状況へと変化するのである。その時、何が起きるのか。明らかなことは、過去の巨大な都市圏の形成は、選ぶ余裕もなくすきまを埋めるようにスプロールしていったが、これからは選ぶ余裕の中で、地域は変貌していくことになる。東京の開発は城南地区を初めにして、時計回りに進められ、一回りすると、今度はその外側にさらに時計回りに開発が進むという形で市街地を外側へと発表させていった。それは量的拡大の中でマーケットメカニズムが生み出した必然であったともいえよう。しかしながら、ひとたび供給量が需要量を上回ると、このメカニズムはくずれる。
その結果、人々は自らの嗜好に合った居住地選択の裁量が与えられ、企業はより目的に合致した地域への立地が可能となり、そして、各自治体は、自らが、こうした動きに対して指をくわえて手をこまねいていないで、自助努力をしなければならない立場に追いやられる。そこに良い意味でも、悪い意味でも、都市圏内における自治体の攻防が始まるのである。
都市圏全体の都市構造のあり方は、分散政策の終着点としての「分散型ネットワーク構造」という枠組みが示されている。その枠組の中で、果たしてポジション取りができるのか、否か。各自治体は、いよいよ、その最終決着を迫られる状況に置かれたのである。
(3)都心回帰と郊外の変質
まず、現在までの大都市圏の発達とそこでの政策をみていく上で、大都市圏における郊外の住宅の存在を考える必要がある。「田園都市構想」という英国人E・ハワードが1902年に提案した有名な構想がある。大都市というのは、郊外に田園都市をつくって中心都市と鉄道で結び、郊外都市は自給自足にする。その郊外都市は人口3万2000人で、3万人が都市住民、2000人が農村人口と考えた構想である。20世紀の大都市圏計画の出発は、ほとんどがこの考え方が基本といっておかしくない。母都市があって郊外都市があるという相互依存関係となっているが、このときの発想は、郊外都市から母都市への通勤は特に考えておらず、郊外都市は自給自足で、必要があれば母都市へでかけて行く形態である。実際、大ロンドン計画もこの流れの中にあり、母都市があって、その市街地周縁にグリーンベルトがあり、更にその外側に衛星都市がある。ただし、実際の計画における大きな違いは、ハワードは中心都市が5万8000人、田園都市が3万2000人で、だいたい2対1の比率で考えていたが、実際は母都市が500~600万人で郊外都市が20~30万人のレベルなので人口規模のスケールが違っていた。しかし、中心都市の存在と郊外都市の位置づけという考え方はだいたい同じであった。これは、われわれが20世紀に考えていた大都市圏の典型的な住まい方である。
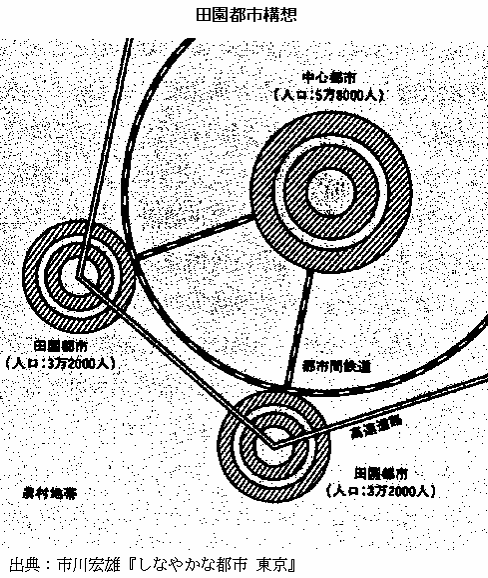
では、東京はどうであったか。住むところが短期間に外側に広がってスプロール化し、さらにはるかかなた、通勤時間1時間半から2時間の遠くの場所にまで移ってしまった。郊外に自然を求めて住宅を持つという考え方が根底にあったからだといえば確かにそうかもしれない。しかし、その結果、人々が郊外に移り住んでしまった都心は空洞化してしまったのである。これから、都市圏全体で人口が増えるというプレッシャーが減るのであれば、この考え方はもはや考え直さなければならないことになる。都心は最も基盤整備の水準が高い。昼間の基盤整備で300万人が住めるのにもかかわらず、夜になると60~70万人になってしまうのである。そこにはあと200万人入っても大丈夫なだけのインフラが存在しているのである。インフラがありながら住まない。この矛盾は何かということに気づくべきなのである。
ハワードが考えていた田園都市とは、豊かな自然にあふれた、質的にレベルの高い住宅に住むことであった。大都市圏に住んでいるサラリーマンの実態は、郊外にいっても庭は小さくて、周辺の基盤整備のレベルは低く、通勤混雑があって、通勤時間が長い。一方、都心には基盤整備をしなくても住める場所がいっぱいある。しかしそこには郊外に存在するような自然はない。
そうであるならば、これからは、郊外に出る限りは、自然は豊富で住宅も立派だという環境が叶えられるべきで、それによって、結果的に都心の居住の推進と郊外の住宅の質的整備という二方面の政策に重点が置かれることが必要となる。現状は、多くの郊外住宅地で衰退が始っている。ちょうど昭和40年代、50年代に、現在50歳代後半から60歳代の勤労者がローンを組んで一生懸命、郊外に庭付き型を買って通勤した。それが今どうなっているかの現実を見なければならない。地域的遍在もあるが、通勤条件の悪いことなどの事情から、その子どもたちは既に郊外に住みたがらないのである。遠いと言って親が住んでいた場所に戻らずに、もっと近い所に家を借りているケースはもはや例外ではない。都心に通う大学生に実施した調査では、親の家に3割は帰らない。あとの3割は売ってしまうという結果となっている。一生懸命に親が築いた場所に対して子どもはあまり執着がない。都心回帰が始まって都心に住むことができるし、郊外はそれほど魅力はないということになって郊外部の衰退に拍車がかかることになる。
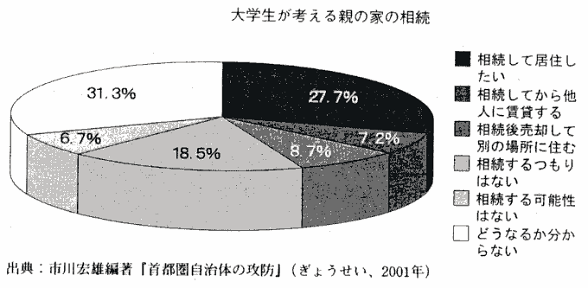
この問題の解決は、都心では現在の基盤のストックを生かし、なおかつ公共空間をつくって都心にない緑をつくっていくなどの住環境の整備につとめて居住者を増やす。一方で、郊外に住む以上は、それにふさわしいゆったりした環境のレベルが必要である。アメリカ型の郊外住宅のレベルに追いつくのは無理であろうが、現在の床面積や敷地の倍増計画が現実のものとならなければならない。大きな数の人口が都心に戻れば地価が下がり、今の価格で倍の面積を買うことができる可能性も生まれる。都心に多くの人が住むことによって、いたずらに郊外に投資をしなくてよくなり、基盤整備の投資の上でもバランスすることになる。
これからの流れは、都心居住の推進と郊外住宅の質的向上という2つの政策の中で、どこの自治体がそれを具体的に受けとめることができるのか、あるいはできずに衰退していくのか、その結果によって自治体間格差が現実のものとなっていくのかがテーマになるであろう。